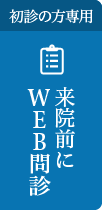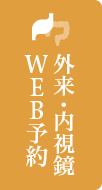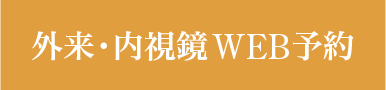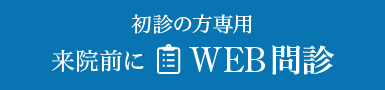逆流性食道炎とは
 正確には、胃食道逆流症(GERD)と言います。胃から食道にかけて胃酸が逆流することで、ゲップや胸焼けなどの症状が起こります。胃と食道の間には、食べ物を飲み込む時以外は閉まって逆流を防ぐ括約筋がありますが、加齢などによって括約筋機能が低下することで、胃から胃酸や食べ物が逆流するとされています。蠕動運動が正常であれば、逆流しても胃に戻す力がありますが、蠕動運動が低下していると胃酸や内容物が長時間食道に留まってしまいます。食道には、胃酸から守る粘液がないため、食道に長く胃酸や内容物が留まることで炎症を起こします。
正確には、胃食道逆流症(GERD)と言います。胃から食道にかけて胃酸が逆流することで、ゲップや胸焼けなどの症状が起こります。胃と食道の間には、食べ物を飲み込む時以外は閉まって逆流を防ぐ括約筋がありますが、加齢などによって括約筋機能が低下することで、胃から胃酸や食べ物が逆流するとされています。蠕動運動が正常であれば、逆流しても胃に戻す力がありますが、蠕動運動が低下していると胃酸や内容物が長時間食道に留まってしまいます。食道には、胃酸から守る粘液がないため、食道に長く胃酸や内容物が留まることで炎症を起こします。
逆流性食道炎の原因
胃と食道の間の括約筋の機能低下と、消化器の蠕動運動機能の低下が主な原因です。さらに、胃酸が多く分泌されると逆流性食道炎を引き起こすリスクが高まります。近年の日本における食生活の欧米化によって、逆流性食道炎の症状を訴える方の割合が増加しています。逆流性食道炎のリスクが高い方の特徴として、肥満や夜食習慣がある方、飲酒習慣がある方などが挙げられます。生活習慣が乱れている方は注意が必要です。
さらに、強い腹圧も逆流性食道炎を起こしやすく、締め付ける衣服や猫背の方もリスクがあります。また、胸部と腹部を分けている横隔膜部分の靭帯や筋肉が緩む食道裂孔ヘルニアのある方も逆流性食道炎になりやすいとされています。
逆流性食道炎の症状
逆流性食道炎の症状は以下の通りです。
- 胸焼け
- 胃もたれ
- 胃痛
- ゲップ
- 胸のつかえ
- 胸の痛み
- 呑酸(酸っぱい物や苦いものがゲップと一緒に上がってくる)
- 吐き気
- 喉の違和感
- 咳嗽
- 喘息
- 耳鳴り
など
咳や喘息の症状は、逆流性食道炎の症状と判断するのは非常に難しいため、長引く咳や喘息の症状、喉の違和感がある場合は、念のため当院を受診することをおすすめします。また、横になると逆流しやすいので注意してください。
逆流性食道炎の検査
胃カメラ検査で、食道の粘膜を直接観察します。自覚症状と粘膜の所見が一致するとは限らないので、内視鏡検査で状態を確認することで正確に診断し、適切な治療を行うことができます。逆流性食道炎の症状は、稀に食道がん・狭心症・心筋梗塞などの疾患の症状として現れる場合があるため、医療機関を受診し検査を受けることが非常に大切です。食道粘膜がただれる・白っぽくなる・赤みがある・潰瘍などが確認できた場合は、その症状や所見に適した治療を行います。
逆流性食道炎の治療
生活習慣が大きく影響している疾患のため、薬物療法と同時に生活習慣の改善が必須になります。逆流性食道炎の症状は、お薬の服用で簡単に改善・解消できます。しかし、再発しやすい病気のため、食生活を中心とした生活習慣の改善を行います。医師の指示に従って、無理のない程度で生活習慣の改善を行いましょう。
生活習慣の改善
- 脂肪分の多い食事や消化に時間がかかる食事を控える
- 胃酸分泌を促す食べ物を控える
- 暴飲暴食を控え、腹八分目に抑える
- アルコールや喫煙、香辛料などの刺激の強いもの・酸味の強いものを控える
- コーヒー・紅茶・濃い緑茶などのカフェインを控える
- 就寝前2~3時間は食べない
- 間食をやめる
薬物療法
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー・プロトンポンプ阻害剤・H2ブロッカーなど胃酸分泌抑制剤や消化管運動賦括剤などによる治療を行います。受診し、検査を受けることで他の疾患を発見できたり、適切な治療を行ったりできるので、逆流性食道炎の症状が気になる方はお気軽に当院までご相談ください。
その他
生活のなかで、逆流性食道炎の症状が出ないように気を付けていきましょう。具体的には以下の通りです。
-
ガードルやコルセット、きついベルトや帯など、締め付ける衣服を身に着けないこと。
-
猫背に気を付けること。
-
前かがみの姿勢や仕事をなるべく避けること。
-
禁煙・節煙を行うこと。
-
食後2時間以上はあけてから就寝すること。
※横になると症状が出やすい場合があるので、クッションなどで上半身を高く起こしながら横になってみてください。または、左半身を下にして横になることもおすすめします。